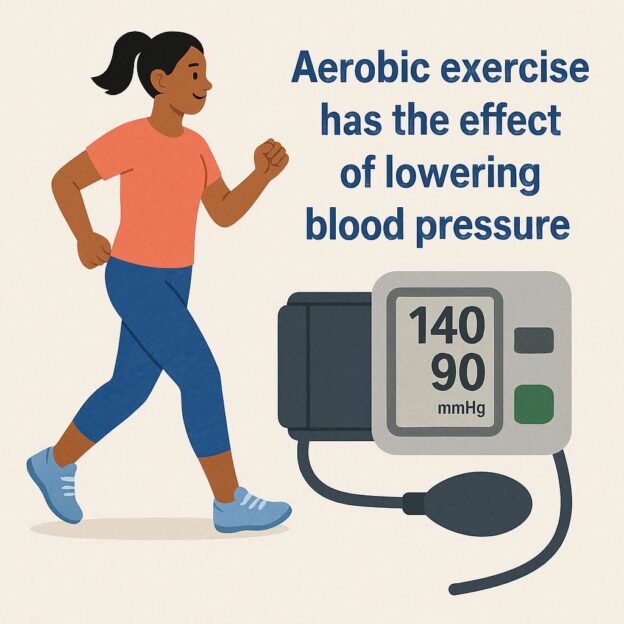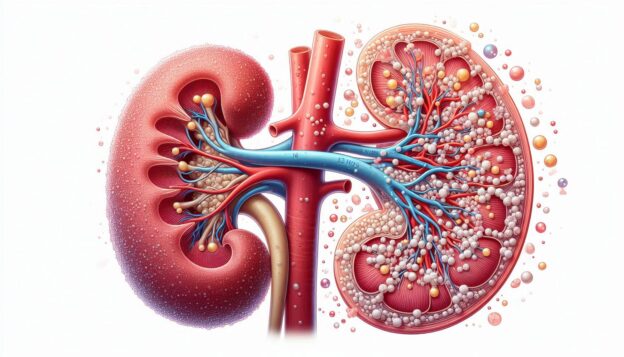有酸素運動 降圧効果 がある 適度な運動を取り入れることの大切さを紹介します。日頃、運動をしている人は、一般的に血圧が低いことがわかっています。軽く汗ばむ程度の有酸素運動が効果的です。特に運動不足の人は、毎日の生活のなかでも積極的に歩いて、運動量を上げることを心掛けましょう。
有酸素運動 降圧 効果で血圧を下げる
有酸素運動は、高血圧の予防と改善に効果的な非薬物療法として広く認識されています。ウォーキングやジョギングといった継続的な有酸素運動は、血管の柔軟性を高め、自律神経のバランスを整えることで、血圧を安定させる効果が期待できます。
10週間ほど運動を続けると血圧はさがる
汗ばむ程度の軽い運動を毎日30分続けると、10週間で半分以上の人は収縮期血比が20mmHg、拡張期血圧は10mmHg低下し、平均でも11/6mmHg低下すると言われています。軽い運動を毎日続けることによって、薬物治療を必要としなくても、血圧を下げることができる人も多いのです。
運動の種類は、短距離をを全速力で走るような激しいものはよくありません。軽く汗ばむ程度の早歩きやジョギング、水中ウオーキングなどの有酸素運動がお勧めです。特にこの運動をしなければいけない、というものはないので、毎日続けて行える運動がいいでしょう。1駅分歩くなどもいいでしょう。
生活の中に歩く時間を増やす
とはいえ、運動が必要とされる多くの人は、運動好きでないことが多く、スポーツとして行う運動は長続きしないことが少なくありません。何もスポーツジムや運動場で行うものだけが運動ではありません。誰でも簡単にできる運動として、*毎日30分以上の早歩きをお勧めします。
「ただ歩くだけでは面白くない」「夜は仕事で遅くなるから歩く時間がない」という人は、まずは毎日通勤時にひと駅手前で降りて歩いたり、エスカレーターを使わずに階段を上り下りして、生活の中に歩くことを多く取り入れるようにしましょう。
休日などに長い距離を歩くときは、景色のよいコースを選んだり、小さなミュージックプレイヤーを持ってイヤホンをつけて歩けば、退屈せずに楽しみながら歩くことができます。1日30分続けて歩くことが無理な場合でも、10分ずつ細切れに歩いてトータルで30分歩くのでも構いません。特別に時間を作らなくても、生活の中で積極的に体を動かすようにしていく工夫が大切なのです。
週1日の集中型では効果は得られない
週末はゴルフやトレッキングなど長時間運動している人は、それだけで十分な運動量を得ていると思いがちです。しかし、週に1 回では血圧を下げる効果としては不十分です。せめて週3 日以上は運動を行うようにしましょう。
1日30分の早歩きはダイエットにも最適
肥満解消のために運動は欠かせません。ゆっくり脂肪を燃焼させる有酸素運動を習慣的に行えば、必ずやせられます。継続することで太りにくい体を作ることもできるのです。
高血圧治療のガイドラインにおいても、有酸素運動は食事療法や薬物療法と並ぶ重要な治療法の一つとされています。
有酸素運動が血圧を下げる仕組み
- 血管の柔軟性向上: 有酸素運動を継続することで、血管の内皮機能が改善され、血管が広がりやすくなります。これにより、末梢血管の抵抗が減少し、血圧が下がります。
- 自律神経のバランスを整える: 運動によって、血圧を上げる交感神経の働きが緩和され、血圧が下がります。
- 体重減少: 肥満は高血圧のリスクを高めますが、有酸素運動は体脂肪を燃焼させる効果があるため、体重減少によっても血圧が下がります。
- インスリン感受性の改善: 運動によってインスリンの働きが改善され、高血圧を含む生活習慣病全般に良い影響を与えます。
- 体内の塩分排出促進: 運動によって汗をかき、体内の余分な塩分が排出されやすくなります。
どのくらいの運動が効果的か
- 種類: ウォーキング、軽いジョギング、水泳、サイクリング、水中ウォーキングなど、全身を使う有酸素運動が推奨されています。
- 強度: 少し息がはずむ程度(「ややきつい」と感じる程度)の中等度の強さが目安です。息をこらえたり、激しすぎる運動は一時的に血圧を上昇させる可能性があるため、避けるべきです。
- 時間と頻度: できれば毎日、合計で30分以上行うことが推奨されています。1回あたり10分以上の運動を複数回に分けても効果があるとされています。
注意点
- 運動を開始する前に、必ず医師に相談し、自身の健康状態に合わせた運動量や内容についてアドバイスをもらいましょう。
- 特に重度の高血圧の方や、心臓、腎臓などに疾患がある方は注意が必要です。
- 運動中に気分が悪くなったり、血圧が著しく上昇する場合は、すぐに運動を中止してください。
有酸素運動は、血圧を下げるだけでなく、血糖値や脂質のコントロールを改善するなど、全身の健康に多くの良い効果をもたらします。無理のない範囲で、日々の生活に取り入れることが大切です。